
鈴木成一と本をつくる#3 「感性を磨け。自分が喜ぶものに触れよ」
「超実践 装丁の学校」(本屋B&B)は、これまで1万冊超の書籍を装丁してきたブックデザイナー鈴木成一氏が、”ガチ”で後進を育てるために開講されたワークショップです。全5回のうち、第3回講義の模様をお届けします。(#1へ/#2へ)
イラストとタイポが殺し合わないために
梅雨の湿気と連日の猛暑にうんざりな7月上旬だったが、この日は若干暑さが和らいだように感じる。前夜に続き、下北沢の本屋B&Bでは鈴木成一による「超実践 装丁の学校」が開かれた。
今夜は「ラフ講評」後半戦だ。初回講義からわずか2週間余りだったが、どのプランにも試行の跡と、自信の一端が刻まれていた。それに対して鈴木は真摯な批評と的確なアドバイスを打ち返し、発表者たちを静かに鼓舞するのだった。
この夜も、まずはミニ講座からスタートする。前日は、装丁におけるエンターテインメント小説らしさとは何か、ということについてだったが、今日は題字、つまりは「タイポグラフィ」についてのレクチャーだ。昨日の「ラフ講評」で鈴木が指摘した「イラストとタイポ(グラフィ)が殺し合う」という感覚について、より詳しく解説された。
鈴木は自ら手がけた書籍を例に語る。まずは町田康『入門 山頭火』(春陽堂書店)だ。装画を担当したのは、かつて開催されていた「鈴木成一 装画塾」で見いだされた根木悟。彼の描いた装画は濃い青と黒で彩られ、その知性と野性が拮抗した画面は、山頭火の人生を彷彿させる。鈴木はその装画に、「筑紫アンティーク明朝」と呼ばれるフォントで書名を載せた。「昔の活字」のような風情あるフォントだが、さらに文字に刻みを入れ一文字の中にズレを加えたことで、根木の装画とのシナジーが高まっている。

「根木さんの絵が期待通りだったので、そこにある種、引きずられるかたちで生まれたタイポです。筑紫アンティーク明朝は、絵のラフな感じ、荒っぽさに合ったフォントですよね。さらにこのフォントで書かれた『山頭火』の文字を刻んでズラし、ノイズを与えるという演出で、山頭火の一筋縄ではいかない殺伐とした、無頼性を表現しました。装画とタイポの相乗効果によって、一つのコンセプト/メッセージを打ち出す。これがブックデザインの基本ですね」
絵を読み解くことで”法律”が見えてくる
続いて、須藤古都離の小説『ゴリラ裁判の日』(講談社)を引き合いに出す。「メフィスト賞」を受賞した著者のデビュー作であり、人間並みの知性を持ったゴリラが、銃殺された夫のために裁判を起こすというエンターテイメント作品。この装画を担当したのは、鈴木が審査委員を務めるイラストコンペ「HBファイルコンペvol.33」で鈴木成一賞に輝いた田渕正敏だ。顔がない人間たちの塊から、青の繊細な曲線で描かれたゴリラがにょきっと立ち上がり、力強い印象を与えるイラストだ。
装画を依頼する際、具体的な要望を出さず、原稿を読んでもらったうえで感じたものをイラストにしてもらう鈴木だが、この絵に関しては「夢でこんなを絵を見ていたからビックリ」するほどイメージ通りだったという。そのイラストに合わせて、「ゴリラの斜め上へ向かう勢い」を活かしたタイポグラフィを添えた。
鈴木は「イラストの世界観を読み解くことで見えてくる『法律』にのっとることが大事です」と強調する。鈴木はたびたび「装丁には正解がある」と言うが、「法律にのっとる」という言葉からも、その哲学が窺える。

連続殺人事件と犯人の少女の父親である警察官の”罪”を描くエンターテインメント小説『無限の正義』(中村啓・著、河出書房新社)では、物語の舞台となった池袋の夜景写真に、モリサワの「秀英初号明朝」でタイトルを記す。さらにその文字の縁にノイズを加え、さらにデザイン加工でフィルターをかけて写真に馴染ませた。

小田雅久仁『残月記』(双葉社)は、「月」をモチーフにした短編集だ。鈴木は本書の顔に日本画家、釘町彰の作品「snowscape(蒼茫)」を据えた。タイトルは金の箔押しを施し、さらに「月」の字の左上を輝かせるギミックによって、カバー上に表れていない月のイメージをむしろ際立たせることに成功している。

テキストを読み解き、イラストを発注する。そしてあがってきたイラストを、鈴木はまたも読み解き、ふさわしいタイポグラフィについて考えるという。本の個性をかたちにする装丁の技の数々が矢継ぎ早に紹介され、受講生ともども筆者の私も圧倒されるが、本番はこれからである。
「キャッチーでポップなんだけど、不条理さもある」
『誘拐ジャパン』は、総理大臣の孫である英俊を誘拐した犯人たちが、政治改革を要求するという筋書きだ。「誘拐」や「政治」といったテーマを、著者の横関大は、持ち前の軽やかな語り口とユニークなキャラクターたちの群像劇で読ませる。
受講生たちはシリアスでありながらコミカルな『誘拐ジャパン』の二面性を、ひとつのデザインでいかに象徴させるか、という難しい問いにチャレンジすることになる。
後半戦でまず鈴木を唸らせたのは、松山千尋のタイポグラフィだ。淡い色のカバーの至るところには、登場人物らしき数々の人物イラストがちりばめられている。そしてど真ん中に書名がある。「誘拐」と「ジャパン」の文字は上下に分かれているが、各文字は点線で、かすかに輪のように繋がっている。
「誘拐」のタイポは、食パンの袋を閉じる「バッグ・クロージャー」のようだったり、子ども用のブロック玩具「Gakkenニューブロック」にも似ていたり、ユニークである。また、「ジャパン」のほうも、波のようなシルエットで勢いを感じさせる。極めつけは「パ」の半濁点だ。丸がライフルのスコープのようになり、その中に誘拐のターゲットとなる子どもの姿がある。

コミカルとシリアスのバランスが見事な松山の作字に対して鈴木は「このタイポだけで十分勝負できるね。キャッチーでポップなんだけど、不条理さもある。非常に完成度が高いです」と語った。予想外の高評価を噛みしめるように唇をギュッとつぐんでうなずく松山が、若干感極まっているようにも見えた。
ただし、松山のこだわりについては「待った」がかかった。カバーに散らばるキャラクターたちを、表で動く人物と、水面下で暗躍する者に分け、トレーシングペーパー(半透明の用紙)で表現したいというのだ。また松山は、2案目で目元を腕で隠した人物の顔をクローズアップにした表紙を提案したが、ここではオフメタル(アルミホイルのような鏡面的な輝きをもつ用紙)を使用したいそう。
この構想について鈴木は、「ハシゴを外すようなこと言って恐縮ですが、トレペやオフメタルを使うとなると、それはもう工芸品を作るアイデアでしょう」と、たしなめる。印刷の再現性が低いトレーシングペーパーやオフメタルは、軽々しく手を出せるものではないそうだ。
しかし鈴木は代案を出すことも忘れない。「トレペは柔らかくて優しい感じになるので、鋭角的なデザインを目指すなら、もうちょっと硬質な半透明のフィルムのほうが合うんじゃないでしょうか」と語った。
進行役の編集者・柏原航輔からは、昨日もいくつかあったキャラクターの相関図的な見せ方への疑問が呈された。これには鈴木も同意し「物語を全然知らない人が見て、この本の性格として受け取れるものがあるのだろうか。読んだ感想をもっと消化したうえで、いちばん伝わりやすいものを考えてみてください」と応答した。この見解を踏まえて、松山は次回どんなアプローチをするのか。あの見事なタイポが活かされるかも注目だ。
次に鈴木が関心を示したのは、行川雅代の装丁案だ。4案も出した彼女だが、誘拐事件の犯人グループの4人と、ターゲットの子ども、そして劇中に登場する犬が駆ける様子を、真上から俯瞰して見せるイラストがハマった。走るキャラクターたちの姿は影になっているのだが、鈴木は「これはおもしろい」と言って、さらに続ける。
「登場人物の姿がシルエットになっていることで、何事かが起きていると想像させるのはアリだと思う。影になった登場人物たちが走る姿を俯瞰で見せることで、この物語の疾走感とシリアスさを演出できています」
別のイラストレーターを起用した、やや漫画テイストの装丁案もやはり疾走感があり、なにより力があった。ただ、いずれにしても、「タイトルロゴはここから頑張りましょう」と鈴木は付言した。次の段階で、イラストとタイポの相乗効果をどこまで高められるかが行川の課題だろう。
だからどうした?
後半戦では、本という物体だからこその仕掛けを模索する受講生も見られた。木下悠は、PPシートというクリアファイルなどに使われる0.2ミリの厚さのカバーを使用。カバーを外すことで、絵柄が変化するという遊びを取り入れるという。カバー有りだと男の子は縄で縛られているが、カバーを外すとサッカーボールで遊んでいる絵に変わる。主要キャラクターの英俊のふてぶてしさ、肝が据わった子どもであることを示す意図だ。またその子ども自身、人の頭のかたちを象ったシルエットの中にいるため、誘拐犯の存在を示唆する。
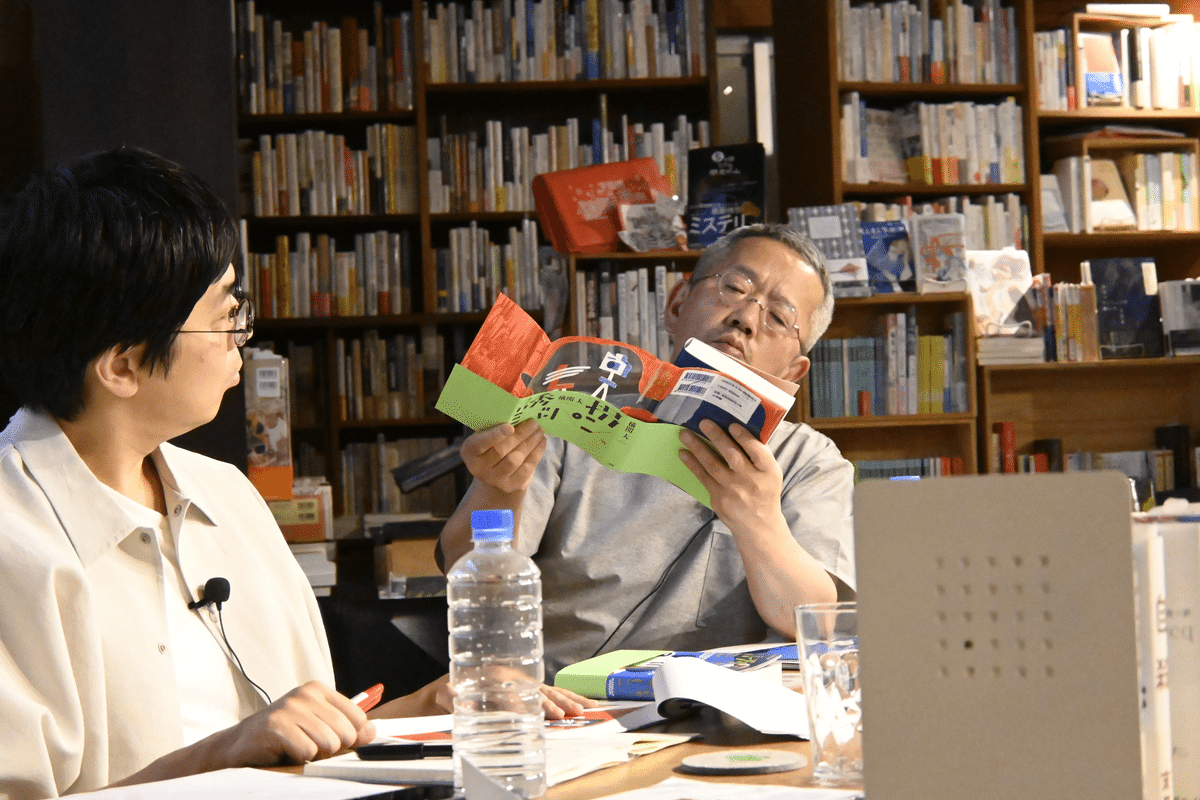
遊び心たっぷり、イラストのキャッチーさもあいまって印象に残る装丁案だ。しかもすでに試作品まで持ってきている。これは高評価だろうと思いきや、鈴木は「興味の対象としてはいいですが・・・・・・だからどうした?っていう感じもありますよね」と手厳しい。
2案目も、正面を向いた男の子の顔が、帯を外すと表情が変わるというギミックを取り入れたユニークな仕上がりだが、鈴木は「たしかに絵はキャッチーでシンボルになる強さがある。勢いは伝わってくるんだけど」と腑に落ちないようだ。
「イラスト自体は、ちょっと手塚治虫っぽい昭和レトロな感じもあるし、ピカソの絵のように、異なる表情が一つの顔に同居してるみたいでもあり、面白いです。絵の世界観は強力で新しい感性なので、これを利用しない手はない。ただ・・・・・・PPシートの仕組みはどうなんでしょう? 一個の本として自立はするんだけど、物語とイラストを繋ぐ装丁と考えると、やや混乱していると言わざるを得ないかな」
筆者としても木下のプランには惹かれるものがあったが、鈴木の講評には納得せしてしまう。鈴木の口調は厳しいものだったが、応募時点のポートフォリオの審査時から、鈴木は木下の装丁に注目していた。期待の裏返しという側面もあるのだろう。木下は「もうちょっと、小説そのものに寄り添ってみます」と一旦退いたが、はたしてどういう形でブラッシュアップするのだろうか。
鍋田哲平は、鈴木もよく知る女性イラストレーターの切り絵イラストを使ったデザイン案をプレゼンする。人工芝の上にイラストレーターが描いた10人の登場キャラクターの切り絵を並べ、真ん中に立つ主人公・美晴のみにフォーカスして一発撮りした写真だという。鍋田はこう説明する。
「切り絵はスキャナーで入力せず、カメラ撮影で奥行きを出しました。登場人物たちの不透明な関係性、周りに渦巻く思惑が表現できるかなと」
これもなかなかの労作だが、鈴木は「彼女の絵をボカすってどうなの?って感じがするんだよね」と切り出した。
「俺が彼女の絵に新鮮さを感じるのは切り絵だからなんですよ。切り絵ってものすごいエッジが立つんですよね。その明快な輪郭をいくつも貼り重ねると、とんでもない不条理が生まれる。そこが面白いわけです。だからボカしちゃうと、もったいないように思える」
すでにブックデザイナーとして活動している鍋田は、この作品を作るに当たって「いつもはイラストレーターさんの自由な発想から出発するんですが、今回は自分のアイデアを全面に出せるチャンスなので思い切ってやってみました」と言う。そんな切実な思いをあっさりと退けるところに、鈴木の厳しさを見た。
しかし、鍋田が提出したもう一つのプランは、なかなかの評価であった。誘拐グループの実行犯3人と犬の横顔が繊細な筆致で、かつ大胆な構図のもとカバー全体に描かれており、その顔がのっぺらぼうであるのもあいまって鮮烈な印象を残す。前傾している彼女たちの先には英俊がいるのだろう、カバーの袖に子どもの後頭部が描かれていた。
「繊細かつグラフィック的な大胆さもあって、非常に目を引きつける絵柄にはなっていますね。文字の組み方もピッタリ合っている」
ただし、肝心の「物語との整合性」に難があるようだ。

「やっぱり毒がほしいんですね。作者である横関さんの茶目っ気と悪意が、装丁からも滲み出るといい。今の2案はどちらも生真面目なので、いたずらというか子どもっぽい工夫があってもいいんじゃないでしょうか」
鍋田がどちらの案を選んで、仕上げていくのか。はたまた第3の案を繰り出してくるのか。技術力があるだけに、期待も膨らむ。
自分が喜ぶものにたくさん触れよ
果敢にトライする受講生たちのデザイン案を見ながら、本の個性・メッセージ・コンセプトを、ひとつのビジュアルで示すことの困難さを痛感する。
「一言で言えないから、本を書いたのだ」という物言いがある。そのとおりであろう。簡単には言えないから、何百ページも文字を連ねる。その一方で装丁家たちは、その文章の根幹を鷲掴みにして「これが本質です」とデザインで示さなくてはならない。その行為は一歩間違えると、「他の要素は枝葉末節だ」と切り捨ててしまうような、ある種の暴力にもなりかねない。装丁には大きな責任が伴う。
だからこそ鈴木は、本の個性をミスリードさせかねないデザインに対して、遠回しな言葉は使わない。率直にダメなものはダメだと言う。
登場人物たちの二面性を示すために、誘拐される少年・英俊が、仮面をかぶった姿をドアップで見せるという李生美の案はインパクト抜群だが、鈴木は「ちょっと怪しすぎる」と懸念を示す。「これは京劇のお面ですよね? 能面もそうですけど、お面は重すぎる気がします。お面で素顔を隠すことで非常に重たい内面を想起させて、ミステリアスな方向に傾いちゃう。これではかなり猟奇的な犯罪を想像させてしまいそう」。
初回の講義で『誘拐ジャパン』のテーマを「全員共犯」というキャッチフレーズで見事に要約してみせた小守いつみ。彼女は街の雑踏をラフに描いたが、そのシリアスなタッチの絵を見て鈴木は「社会派というか、かなり深刻な作品をイメージしてしまう」と伝える。さらに角印のごとく四角に収まって、ドラえもん的な目があしらわれたタイトルロゴのかわいらしさには、「絵とちぐはぐな印象でまったく合わない。とってつけたような感じです」と述べる。
こうして受講生たちの装丁プランを見ていくと、冒頭で紹介した鈴木の装丁がいかに考え抜かれたものであったかがよくわかる。全体のラフ講評が終了し、鈴木はこう語った。
「装丁は何がハマるのか、本当にわかりません。どこに正解が転がっているのかわからない。だからこそ装丁家は常に感性を磨き続けるんですよ。多種多様なものに触れて、たくさんの引き出しを持っておくことが重要です。そのときに忘れてはいけないのが、自分が喜ぶものに触れるということ。それが装丁家の個性になりますから」
鈴木が正解を出せるのは、何よりも引き出しの多さによるのかもしれない。だとすれば、来年でキャリア40年を迎える鈴木成一の境地に、受講生たちがかなうわけはない。それでも1ヶ月半にわたって一つの本のことを考え続ける経験は、受講者たちにとって飛躍のきっかけとなるはずだ。

この日、講義終了後に初めて受講生たちの間で懇親会がもたれた。昨日のスタッフ打ち上げと同じように、芋焼酎「鶴見」のロックをダブルで立て続けに飲みながら、鈴木は受講生たちと話し込んでいた。
ウィークデーだったこともあり、終電前にお開きとなったが、タクシーに乗りこむ鈴木の顔には、受講生たちと飲み交わすひとときへの未練が見えた。授業終盤、鈴木は多種多様なものに触れることの重要性を説いていた。こうして若い才能と接することで、自らの感性も磨いているのだろう。それは意識的なものか、無意識的なものか。いずれにせよ、鈴木も受講生たちと同じ土俵に上がっているのだ。
(文中敬称略)
取材・文/安里和哲
写真/平林美咲(鈴木デザイン室)
◎筆者プロフィール
あさと・かずあき/フリーライター、インタビュアー。1990年、沖縄県生まれ。ポップカルチャーを中心に取材執筆を行う。ブログ『ひとつ恋でもしてみようか』。Xアカウント @massarassa

