
西谷格「”ああ苦しい! 辛い!”と何度も呻き、時には叫んだ」一九八四+四〇 ウイグル潜入記 #11
本連載は、上海在住経験があり、民主化デモが吹き荒れた香港のルポルタージュなどをものしてきた西谷格氏による、中国・新疆ウイグル自治区滞在記です。少数民族が暮らす同地は、中国で最も当局による監視が厳しい地として知られています。 ※本編は1週間後に有料へと切り替えます。(#1~#3は無料公開/#1はこちらから)
◆5章 イリ
油断の産物
香港から上海、北京、新疆ウイグルへと徐々にリスクの高いエリアに身体を順応させるように移動していたせいで、鈍感になっていたのかもしれない。警察に何か聞かれても「旅行をしている」と答えれば法的な問題はなく、写真を撮るなと言われれば、素直に削除すればそれ以上面倒なことは起きなかった。
油断というのはいつも結果論で、言葉遊びみたいなものだ。たとえどんなに注意散漫でも、何も問題が起きなければ「大胆だ」「やることに無駄がない」という評価になり、油断とは見做されない。逆に、細心の注意を払っていてもミスが生じたのであれば、どこかに油断があったということになる。謝罪の言葉とともに搾り出される「油断していました」という言葉、あるいは緊張感を持たせるための「油断するな」という言葉は、結局のところ、何も言っていないに等しい。
その意味で、私はいつも油断している。そもそも、リスクに敏感な人間であればフラっと日常の延長で新疆ウイグル自治区を訪れるようなことはしないだろうし、収容所まで行って写真を撮ったりもしない。警察の建物にレンズを向けることすらしないだろう。つまり、この原稿は油断の産物である。
前置きが長くなった。私はとにかく、油断していたのである。
香港で取得した中国ビザの期間は、30日間。期限目いっぱいとなる最終日の夕方に国境の街ホルゴスに到着した。事前にホルゴス市政府に問い合わせたところ、国境は20時まで開いているとのことだったので、間に合うはずだ。
陸路での国境越えは、漠然と香港―深圳間のような場所をイメージしていた。空港のイミグレーションのようなものがあり、通り抜けた先にバスやタクシー乗り場があるのだろうと思っていた。だが、タクシー運転手に国境の出入り口まで行きたいと告げて向かうと、着いた先には巨大なビルと鉄条網のフェンス、そして警察が1人立っているだけだった。警官に話しかけると、残念な返事が返ってきた。
「歩いて国境を越えることはできない。向こうのバスターミナルで切符を買って、バスで移動しなさい。でも、今日は最終便はもう出発したから、また明日来なさい」
ビザの期限が切れそうだと伝えると「どうしようもない。ビザが切れたら、罰金500元(約1万円)を払いなさい」と返された。ビザの期限はいつ切れるのかと念を押して聞くと、どこかへ電話をかけて確認してくれた。
「あなたのビザは、明日の24時まで有効です。明日国境を越えれば、不法滞在にはなりません」
どうやら、入境初日はカウントされないようだ。面倒には思ったものの、ほっと一安心して近くのホテルに宿を取り、翌朝は早めに出発した。そういえば、ホテルの駐車場に「National Geographic」というステッカーの貼られた自動車が停まっていたが、辺境の大自然を撮影に来ていたのかもしれない。

翌日の午前10時頃、バスターミナル近くにはカザフスタンの通貨・テンゲの両替商がうろうろしており、声をかけられた。100元(約2000円)を60テンゲに交換するというので、念のため100元だけ両替しておいた。
ネット情報がほとんどなかったので不安だったが、行ってみると、ホルゴスからはジャルケント(新疆ウイグルのヤルカンドと地名が似ていて紛らわしいが、ホルゴスから西に約35キロのカザフスタン共和国内の小さな町)とアルマトイ(ホルゴスから約400キロのカザフスタン最大の都市)行きの2路線があると分かった。
私はこのとき、チュンジャというカザフスタン南東の町を目指していたので、ひとまず国境近くの街ヤルケント行きの切符を買った。英語でネット検索したところ、チュンジャはウイグル族の人口比率が高く、ウイグル村と呼ばれていると書かれていたからだ。
新疆ウイグル自治区はモンゴル、ロシア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、アフガニスタン、パキスタン、インドと国境を接しているものの、カザフスタン以外は険しい山脈や砂漠で隔てられ、地図で見る限り国境を行き来することは不可能、あるいは極めて困難に思われた。もっとも容易に国外に出られそうなのはイリからカザフスタンへ抜けるルートであり、国境を越えれば、ウイグル族たちに話を聞きやすくなるのではと考えた。『重要証人 ウイグルの強制収容所を逃れて』の著者のサイラグル・サウトバイ氏もこのルートで国外へと脱出した。
カザフスタンは「カザフ人」と呼ばれる中央アジアの遊牧民をルーツに持つ人々の国だ。ウイグル人でもカザフ人でも、新疆から国外へ出た少数民族であれば、きっと何か語ってくれるだろうという確信めいたものがあった。
建物を通り抜けた先にある乗り場からジャルケント行きのバスに乗ると10分ほど移動し、出入境管理所で降ろされた。空港のイミグレーションとほぼ同じような雰囲気だ。
職員がスタンプを押すであろうゲートには中国籍用、外国籍用のほか、興味深いことに「一帯一路専用ゲート」なるものがあった。近くにいた警官に尋ねると、将来的に一帯一路の加盟国のパスポートを持っていれば、優先的に通れるゲートになるのだという。2023年のこの時はまだ運用されておらず、中国社会にありがちな理念先行の状態だった。外国籍ゲートにも人がおらず、中国籍のゲートに並んだ。
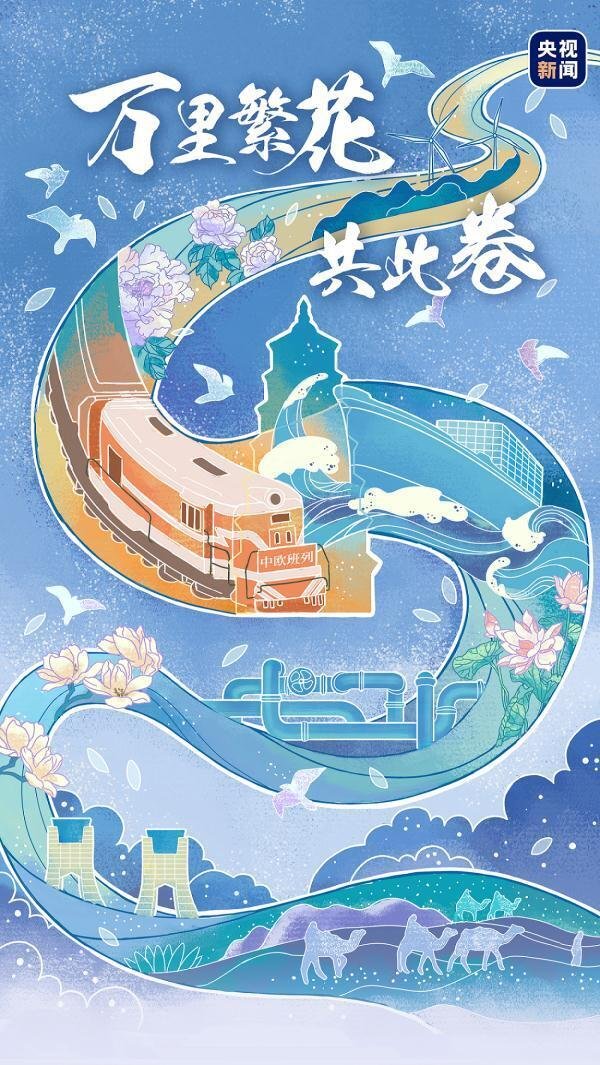
ゲートはかなり混雑していて、少数民族風の顔立ちの人がスーツケースやボストンバッグなど多くの荷物を抱えて並んでいた。話しかけた人は、ほぼ全員カザフ人だった。
順調に列は流れており、10分ほどで自分の番になりパスポートを渡そうとすると、スマホを使って健康検査票と出国カードを記入するよう求められた。いったん列から離れ、ゲート近くに掲げられた看板のQRコードを読み込み、記入を終えた。
再びゲートに向かうと、今度は「少し待て」と言われて係官は遠くのほうへ行ってしまった。私の前方の人々は何の支障も通過していたのに、明らかに対応が違う。非常に嫌な予感がしたのでスマホを開き、オーストラリア戦略政策研究所(ASPI)の地図のスクショなど、問題視されそうな直近の画像を削除した。2〜3分で職員が戻ってくると「ちょっとこちらへ」と促され、壁際の荷物台のある場所へと案内された。
この時、携行品の調査に同意する旨が書かれた書面にサインするよう求められ、言われるがまま署名した。
「荷物を確認しますので、スーツケースとリュックを開いてください。あと、スマホも出してください」
ドキリとしたが、あくまで旅行者として振る舞えば、大きな問題はないだろう。動揺した素振りを見せるのはかえって危ないので、平然と荷物を開いた。着替えや歯ブラシセットなどの間から、何冊かの本が出てきた。中国語の勉強の本や香港のモスクでもらったイスラム教関連の本だったが、小太りで愛嬌のある顔立ちをした30歳ぐらいの男性警官が、一冊の新書を目ざとく手に取った。
「これは何だ? この本は中国では禁書だぞ」
持っていたのは、『新疆ウイグル自治区』(熊倉潤・中公新書)。新疆の歴史について十分客観的に書かれた内容だが、当地でたびたび暴動や抗議運動が繰り返されたことなども記されており、中国共産党にとっては穏便な内容とは言えなかった。何より不穏なのは、副題の「中国共産党支配の70年」の文字だ。「支配」の2文字は、彼らの歴史観と真っ向から対立する。
「新疆の歴史について勉強しようと思い、日本の本屋で買いました」
答え終えたあとも、警官は私のスマホの写真フォルダを恐ろしく念入りに調べている。直近のものだけでなく、最初から最後まで見ようとしているようだ。
「これは何だ? どこで撮影したのだ?」
警官の握るスマホ画面を見た瞬間、しまったと思った。思わず血の気が引いた。写っていたのは、1年ほど前に参加した日本ウイグル協会のイベントの様子で、東トルキスタンの旗が会場前方にデカデカと掲げられていた。
「ええと、日本だったと思います。よく覚えてないですが」
「はっきり答えろ、これはお前が撮影したのか?」
「たぶんそうです。東京でイベントがあったので、行ってみたんです」
「どんな話をしていた? お前はどう思った?」
「よく覚えてないですが……。中国の悪口みたいな話をずっとしていて、私は賛成しませんでした」
写真フォルダをさらにさかのぼると、別の写真も出てきた。22年11月に東京・新宿で行われた白紙革命の様子だ。この時期、中国国内や世界各地の都市部では、中国政府の「ゼロコロナ政策」に反対する若者らが、抗議運動を行っていた。東京ではウイグル族の支援団体や香港でのデモ参加者など、中国共産党の統治に異議を唱える人々が結集し、さながら〝反中デモ〟の様相を呈していた。

「スマホとパソコンは預かる。別の場所に移動してくれ」
事態が非常に悪い方向に進んでいるのを感じたが、どうすることもできない。時間がわからなくなる危険を感じ、リュックから急いで腕時計を取り出しはめた。
建物の奥にある待合室のような場所に通された。ここで再びポケットのなかや靴の中敷きまで細かくボディチェックを受けた。
「この奥に座って待っていろ」
3畳ほどのガラス張りの部屋に入れられ、施錠された。室内は壁がすべて青色のクッション張りになっている。自殺防止だろう。壁の一部が膝下30センチほど出っぱっていて、ベンチのようになっていた。腰掛けると、自分は今、拘束されているのだとはっきり分かった。
ガラス張りの壁の向こうは6畳ほどの広さがあり、あちら側のベンチでは警官2人が常にこちらを監視している。名刺サイズの小型カメラを常時こちらに向けており、撮影し続けていた。
最高刑は無期懲役
ガラス張りの部屋は、警察署内にある留置場だったようだ。留置場に入るとすぐ、弁当が出された。透明なブラスチックの容器に仕切りがあり、白米のほかに3品ほどのおかずが入っていた。まずいことになったという不安と、なぜ写真を消しておかなかったのだろう、なんて軽率だったんだろうという激しい後悔に襲われ、食欲はまったくなかった。
頭では分かっていたのだ。新疆ウイグルに行くなら、中国当局が嫌がるようなメールや写真は、すべて削除しておかなくてはいけない。危なそうな直近の写真は削除していたのだが、古いものはそのままにしてしまっていたのだ。それで特に問題なく動けたので、つい後回しになり結局放置していた。
食べておかないと身体が持たないと思い、ボソボソとした舌触りの悪い白米を強引に口に押し込んだ。おかずは唐辛子を強く効かせた味の濃いものばかりで箸が進まず、トマトと卵の炒めものだけ食べ切った。
待たされている間、飲水と排泄だけは自由だった。この2つの行為は、留置されている間の楽しみとなった。食事を終えて2〜3時間ほど待たされた後、取調室へと通された。
大きな事務机にパソコンが置かれ、3メートルほど距離を置いて、特殊な椅子が置かれていた。思わず目を見張った。カザフ人脱疆者の手記『重要証人 ウイグルの強制収容所を逃れて』などで四肢を拘束する恐ろしい拷問具として書かれていた「タイガーチェア(老虎凳)」が、無造作に置かれていたのだ。
青色の金属製で、背もたれが直角の硬い椅子には小型のテーブルが設置され、テーブルと足元には手足を拘束するリングがあった。ここに座らされるのだろうかとぞっとしていると、背後から警官の一人が「こいつはそっちに座らせろ」と言い、タイガーチェアの隣にある事務用の黒い椅子に座らされた。

私の家族構成、学歴、職歴、仕事内容を細かく聞かれた。現在の職業はこれまで同様に「翻訳業」と答え、3週間ほど新疆ウイグルを旅行したと答えた。旅行の間、どこに行き、誰とどんな話をしたかと詳細に聞かれた。
日本ウイグル協会との関係や、新宿で行われたデモとの関わりについても、しつこいぐらい何度も聞かれた。2時間ほどでいったん取り調べを終え、再びガラス張りの留置場に入れられた。
「お前には『国家安全危害罪』の疑いがある。ああいう写真を所持することは中国では許されておらず、完全に違法だ。最高刑は無期懲役となる」
取り調べを終えて留置場に戻る直前だっただろうか。最初にスマホをチェックした小太りの警官が、私に紙を見せながらこう言った。「国家安全危害」というおどろおどろしい文字が確かに手書きで書かれていて、もはや現実のものとは思えなかった。
「日本の警察は怖いか? 中国の警察は優しいだろう? 海外の警察はひどいからな。特にアメリカの警察は市民を窒息死させるだろ。それに比べたら、中国警察は実に善良だ」
日本の警察のほうが遥かに温厚で善良です、と言いたいところだったが、黙って頷いた。
再び2〜3時間ほど待たされると、晩御飯の弁当が出された。今度は白米に激辛の肉炒めを載せたもので、ほとんど食べることができなかった。時刻が深夜0時近くなったので、
「今日でビザが切れるのですが、大丈夫でしょうか? 今夜、私はどこで寝ることになるでしょうか?」
と質問したが、「ビザのほうは問題ない。どこで寝るかはまだ分からない」との返事だった。
取り調べの間、「弁護士を呼びたい。あと、日本大使館にも連絡を取りたい」と伝えたが、
「我々は24時間以内は弁護士なしで取り調べが可能だ。日本大使館にも、一定期間を超えたら連絡することになっているので、その時はこちらから連絡をする」
と説明された。考える時間を確保するためにも、日本語の通訳を呼んでくれと頼もうか迷ったが、伊寧から連れてくることを考えると、さらに余計な時間がかかるだろう。とにかく早く終わらせたいという思いから結局、中国語のまま続行してしまった。
取り調べの間、気掛かりだったのは私のライターとしての過去の活動が知られることだった。記者のようなことをしているとバレたら、また別の角度から追及されるだろう。そちらまで拡大しないことを祈っていた。
待たされている間、警官同士の会話で「彼の状況はどんどん悪くなっている」という言葉が聞こえ、とても嫌な予感がした。深夜0時を回り、もう今日はホテルで寝ることはできそうにないなと思った。たぶん、そろそろ寝させてもらえるだろう。そう思っていたら、深夜1時過ぎから、2回目の取り調べが始まった。再び、タイガーチェアの置かれた取調室へと通された。
40代半ばぐらいの強面の私服警官が入ってきた。浅黒く精悍な顔つきで、ワイシャツに黒っぽいジャケット姿だった。腰掛けながら、鋭い口調で質問した。
「お前、昔ホストクラブで働いたことがあるな?」
その質問で、すべてを悟った。私の経歴をネットで細かく調べたようだ。それにしても、そこから聞かれるとは思わなかった。私はかつて、2014年頃に上海のホストクラブに1カ月ほど在籍し、ホストとして働いたことがあったのだ(詳しくは『ルポ 中国「潜入バイト」日記』参照)。中国社会の大らかさ(あるいは適当さ)に助けられながらさまざまな職業体験を行い、中国社会を考察したものだ。

出版当時は、中国と日本のネット空間には一定の隔たりがあり、私の著作内容が中国社会に知られることはなかった。だが、2020年頃、中国に住む友人から「あなた面白いことやってるんだね」というメッセージとともに中国語で拙著を紹介したまとめサイトが送られてきて、驚いた。恐らく、翻訳ソフトの機能が向上したことや、日中間の人的往来が一層高まったことなどが背景にあるのだろう。警官たちは私の氏名をネット検索し、そこから芋づる式にプロフィールなどを見つけたに違いない。プロフィールや書籍のタイトル程度なら、翻訳ソフトで十分間に合うだろう。
「ホストクラブ、それから日本料理店での料理人、遊園地の劇団員、ドラマの俳優。お前はずいぶん経験豊富だな。しかも『潜入』したそうじゃないか」
職業や収入源、取引先なども詳しく聞かれた。過去記事のなかからできる限り政治色の薄い、エンタメ系の記事を思い出して答えた。適当に嘘を混ぜようかとも思ったが、相手は被疑者の心理状態などすべてお見通しという様子で、
「我々はすべてを調べることができる。もしもお前が嘘を言ったら、それはすべて分かる。そうすればお前は信用を失い、犯罪容疑は一層深まる。すべてはお前次第だ。分かるよな」
と釘を刺された。
「お前、記者という言葉を意図的に避けていないか? お前の旅行は、どう見ても普通の旅行ではない。お前は記者として取材をしていたんじゃないのか? 記者証はあるのか?」
中国では、記者活動は免許制となっており、政府公認のメディアに属していない者は取材や執筆をしてはいけないことになっている。特に、政治や外交に関わるテーマは厳格に適用されるようだ。
「これまでに書いた本をすべて言え。それぞれどんな内容だ?」
一冊ずつ答えていると、これまでの中華圏での取材が思い出され、何かの総決算を迫られているようだった。自分の身の上に何か重大なことが起きている。でも、その渦中というのは意外なほど日常と地続きで、とても平凡な出来事のように思えた。
「お前は6月4日に香港に来ている。なぜその日に香港に来たんだ?」
6月4日の天安門事件の日に、香港社会の変化があるかどうか見たいと思ったと答えると、警官は何やらわざわざしく頓狂な声を発して、
「それじゃあ、お前は6月4日は政治的に敏感な日だと分かって来たんだな?」
と念を押すように言う。大仰fな口調が威圧的で、何か小馬鹿にされているようでもある。
「ああ苦しい! 辛い!」
スマホの写真や検索履歴も隈なくチェックされてしまった。
「お前はキリスト教の教会にも足を運んでいるな? モスクとか教会とか、宗教に興味を持った理由は何だ?」
「お前は反中勢力から依頼を受けたり、金をもらったりして、スパイに来たんじゃないのか?」
「『新疆 スパイ』と検索した履歴がある。スパイという単語を検索した理由は何だ?」
さっきまであんなに眠かったのに、深夜3時を過ぎると変に目が冴えてテンションがおかしくなっているのが自分でも分かった。途中から「腕時計を外せ」と命じられた。室内にはデジタル時計があったものの、30分ほどズレており、時間の感覚も狂い始めていた。
時々、急にふっと身体が軽くなって1秒間ほど現実感を失うことが何度かあった。その瞬間は目の前の景色は現実ではなく、想像の世界のように思えてとても楽になった。拘禁反応かもしれない、と思った。でも、すぐに現実に引き戻されて圧倒的な疲労と睡魔、空腹、そして恐怖が迫ってきた。ここで受け答えを間違えたら、長期間拘束されてしまう。
近年は毎年のように日本人が拘束され、期間は数年〜10年以上に及んでいる人もいる。たった1日でもこれほど苦しいのに、年単位で自由が奪われ罵倒され続けたら、いったいどうなってしまうのだろう。そもそも、この取り調べはどのような手順があり、いつ終わるのだろう。質問をしても「もうすぐだ」「詳しいことは我々も分からない」「まあ待て」「すぐ終わるから大丈夫だ」としか返されないのだ。
恐怖に耐えるには、死を覚悟するほかなかった。もうこの身体も生命も、自分のものではない。自分はもう死んだも同然だ。そう思うと、少しだけ気持ちが楽になった。日本にいる両親や家族、友人は心配するだろう。明日か明後日には「日本人ジャーナリスト、新疆で拘束」といった第一報が報じられるかもしれない。そしたら、きっとネット上で「自分勝手に危険な場所に行って、日本政府に迷惑かけるな」等々、叩かれるだろう。
写真を消してさえいれば、今頃とっくに国境を越えていたはずだ。これまで出会った何人もの人々を、私のせいで危険に晒すことになってしまったかもしれない。申し訳ない気持ちでいっぱいになり、今すぐ消えてしまいたかった。せめて、目をつぶってしばらく横になりたい。
全身がだるく、頭は後頭部が痺れるような痛みがある。視界は常に揺れたようになっている。
「眠いです。寝させてください」
「駄目だ。今は寝ることはできない」
寝られないというのは非常に辛く、拷問のようだった。頭がボーッとなり、とてもまともな受け答えなどできない。こう答えたらどうなるか、などと先を読む力がなくなり、ものごとを計算できなくなってくる。
もう一つ恐ろしかったのは、拷問を受けることによって自分の人格まで破壊されそうになることだった。この状態が何日も続けば、身体がボロボロになるだけでなく、精神的にも別人のようになってしまうだろう。その時に、他人を思いやったり誰かに親切にしたり、冗談を言って明るく笑ったりという私の内面の良い部分が、根こそぎ失われてしまうような恐怖があった。肉体と精神はつながっている。彼らの手にかかれば、人間一人の精神を改造することなど、容易いことなのかもしれない。
さまざまな角度から質問責めにされた。なかでも「なぜ新疆に来てこんなことをしたのか?」という”動機”部分には、長い時間が割かれた。だが、何度掘り下げて聞かれても、「興味があった」としか答えられなかった。
「またそれか。興味があった、気になった、見てみたかった。お前はさっきからそればかりだ。今回の渡航に、いったいいくら使ったんだ? どこの世界に、興味だけでそんなことをするやつがいると思うか? そんな話を誰が信じるというんだ」
一冊の本にまとめられたらいいなという淡い願望はあったものの、編集者に相談もしておらず、出版の見込みはまったくなかった。本にならなかったら、それでもいい。まずは行ってみよう。おどろおどろしい話ばかり伝わる新疆ウイグルは、どんな場所なのか。渡航理由を考えれば考えるほど、「興味」としか言えなくなる。だが、当局はそれでは納得しなかった。
「お前の話を聞いて、はい分かりましたと言うわけがないだろう。日本ウイグル協会のイベントと関係があるんじゃないのか? ないなら、ないと証明しろ!」
「今回の渡航は私一人で計画して、お金も自分の貯金から出しています。新疆は1回しか行ったことがなかったので、興味があって……」
「また興味か! 興味興味と言っている限り、お前は立ち往生だ。この取り調べは永遠に終わらない。それでもいいのか? ほかの原因があるんじゃないのか? よく考えてみろ」
そう言い残すと、取り調べ官はどこかへ行ってしまい、30分ほど放置された。監視役はずっとついている。いったいいつまで続くのだろう。時計は午前4時か5時を表示していたが、時間の感覚はとうに失われ、意識は極端な覚醒と混濁を繰り返している。
「ああ苦しい! 辛い!」と日本語で何度も呻き、時には叫んだが、監視役は無表情のまま動物を観察するような視線をこちらにチラリと向けるだけだった。
#12に続く(1月末に更新予定です)
◎筆者プロフィール

にしたに・ただす/ライター。1981年、神奈川県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。地方紙「新潟日報」記者を経てフリーランスとして活動。2009年に上海に移住、2015年まで現地から中国の現状をレポートした。現在は大分県・別府市在住。著書に『ルポ 中国「潜入バイト」日記』 (小学館新書)、『ルポ デジタルチャイナ体験記』(PHPデジタル新書)、『香港少年燃ゆ』(小学館)など。

