
清水純一さん「19歳で読書と出会い直すまで」ルポ 読書百景 #2
読売新聞の論説委員を務める清水純一さんは、朝刊一面の名物コラム「編集手帳」の執筆者である。約460文字のスペースで社会事象を鮮やかに評することもあれば、蔵書から抜き出した箴言を世相に当てこむこともある。「読むこと」「書くこと」のプロである彼は、自身の若い頃を振り返るとき、「本がどうしても読めない」というコンプレックスを抱えていた時期があったという。
「本だけではなくて、若い頃には文字を読むのに、すごく苦労する子供だったんです。例えば、国語の教科書を読んでいても、どうしても頭に文字が入ってこないんですね。その感覚を表現するのは、今でも難しい。文章を読んでいても、頭の中はまるでゼロというか、真空のような……。そんな感覚を抱く時期が十代の後半になるまで長く続いたんです」
そんな彼が「読むこと」への苦手意識を克服し始めたのは、19歳の頃に「何故か読むことができた」という一冊の本がきっかけだったという。(取材/文・稲泉連)

文章が「どこかに行ってしまう感じ」
僕が「本」というものに苦手意識を感じるようになったのは、子供の頃に伯父が買ってくれた童話を手にしたときのことでした。
弟は絵本や童話を普通に読んでいるのに、自分はその本のページを開いた瞬間、そこに書かれている文章がいくら読もうとしても「どこかに行ってしまう感じ」がして、どうしても読み進めることができなかった。絵は頭に入ってくるのだけれど、「視覚」の感覚で頭の中が全て埋まってしまい、「理解する」というところまでたどり着けない、と表現したらいいでしょうか。そのとき以来、「本」というものを、どこか遠ざけるようになっていきましたね。
だから、学校での国語の授業もずいぶんと苦労したものです。ただ、この感覚がなかなか上手く人に伝えられないのは、例えば、先生から「朗読しなさい」と言われると、発声して読むことは上手にできたんですよ。でも、それは発声に集中しているからで、文章を理解しながら読み上げているわけではありませんでした。朗読をしていても、内容を理解しながらの朗読を全くしていない――そんな感じだったのを覚えています。
清水さんは小学生の頃、とにかく授業に集中が出来ず、授業中に教室から飛び出したりする子供だったという。後年、新聞で学習に困難を抱える子供たちの特集を読み、自分に当てはまる事例がたくさんあったという。しかし、当時の教育現場にそうした概念はなかった。
学校生活はとにかく机に座ってじっと時計を見ながら我慢している、という記憶ばかりでした。文字だけの本はどうしても苦手でしたが、漫画を読むことはできました。今から考えると、漫画が読めたのは「全体」があらかじめ視覚的に見えていたからだと思います。漫画は絵によって次の展開を少しだけ視覚で予想できるので、「ちょっと先」を想像しながら頭の中で文章を読むことができるでしょう? ページ全体を見ながら文字を追うその「読み方」は、後に僕が本を読めるようになったときの「コツ」と似ていると感じています。
でも、当時はなぜ文字だけになると、内容が頭に全く入ってこないのかが分かりませんでした。すると、読んでいても苦しくてつまらないだけなので、どうしても「本」に対して「俺はこれを読めないんだ」という気持ちが増していく。
一方でその苦しさと裏腹に胸にずっと抱いていたのが、「本」に対する憧れでした。やっぱり、みんながしていることは自分もしたいんですね。だから、読書が面白くないから嫌いだという自分に、コンプレックスを感じていました。
そんな読書に対する苦手意識に変化があったのは、19歳のときに曽野綾子さんの『二十一歳の父』という本との出会いがきっかけです。
当時、NHKの曽野さん原作の連続テレビドラマ「太郎物語」を見たとき、テロップに原作の書名が出てきて、「この本を読んでみようかな」と何故か思ったんですよ。それまでずっと本を遠ざけていたのに、自分がふとそう思った理由は今でも不思議でよく分かりません。とにかく読んでみたい、という気持ちが湧いてきたんです。
ところが、書店に行って新潮文庫の棚に刺さっていた『太郎物語』を手に取ると、本の分厚さにやっぱり怯んでしまいました。それで「これは無理だ」と思って本を戻すと、隣に半分ほどの厚さの本がある。それが曽野さんの『二十一歳の父』でした。
『二十一歳の父』は、裕福な家の次男坊である21歳の学生が、上流社会の堅苦しさに嫌気がさして家を飛び出し、盲目のマッサージ師の女性と結婚するという話です。この夫婦に子供が産まれたことを軸に進む物語を、僕はなんとか読み進めていきました。テレビドラマで『太郎物語』を見たことが、本を読んでみようと思った理由だったからかもしれません。映像を思い浮かべるようにして読んでいると、どういうわけか最後のページまでたどり着けたんです。
そのとき、僕は「読むこと」を必ずしも楽しめたわけではありませんでした。やっぱり「読むこと」は苦しかった。でも、どうにかマンガやドラマを見るように文章を頭の中で映像化しながら物語を読み進めていくと、最後の三行を読み終えたとき、頭が何だかスッキリとクリアになるような感覚を覚えました。大げさな話しではなく、頭を覆っていた薄い膜が剝がれていくようだった、と言ってもいいかもしれません。
そのように僕が「読書」と出会い直せたのは、今から思うとそれが「芸術」や「文芸」というものに意識的に触れた瞬間だったからだという気がします。
一冊の本を自分なりのやり方で読もうとしたことで、綺麗な絵を見た時に「この絵が好きだな」と思うのと同じように、文学を「読む」ということは、その芸術を受け取ることなんだ、とようやく思うことができたんです。
「読む」ことから「書く」ことへ
以来、清水さんは少しずつ「厚い本」を読み進め、自分なりの感覚を探しながら、芥川龍之介や夏目漱石などの日本文学、ドストエフスキーといった長大なロシア文学にも親しめるようになっていったという。そして、二十代になった彼が次第に熱中し始めたのが、社会科学や法律について書かれた本だった。
いま、清水さんは「編集手帳」の執筆者として週に5日間、コラムを書いている。毎日やってくる締切りの日の朝、「何もネタがない状態」から原稿を書き上げる日々だ。
最近では、小説家としての顔もある。社会部時代に長く検察庁などの司法担当記者として働いてきた彼は、直島翔というペンネームで『転がる検事に苔むさず』『テミスの不確かな法廷』といった司法をテーマにした小説を描いてきた。
これまで“読書”が苦手だったからこそ、カラカラに乾いた状態だった喉を水で潤すように、僕は“読む”という行為を捉え直していった、ということかもしれません。
法律がすごく好きになったのは、論理的、体系的に世の中で起こる現象を説明する世界がそこにあったからでした。ある行為がなぜ過失に問われるのか。予見可能性とは何か――。人間の言葉で理屈を尽くして物事を説明するその世界が、どうやら感覚的に好きだったようです。
「書く」ということへの欲求も、「読む」という世界に親しめるようになるうちに、自分の中で形になっていったように感じています。要するに、インプットのやり方を身に付けたことで、アウトプットも「その逆をやればいい」というふうに思ったんですね。
何かを伝えるという行為は、何かを読んで理解することと同じ。適切な言葉をきちんと並べていかなければ、伝えたいことは伝わらない。「読めない」という苦しさを経験してきたことと、数ある選択肢の中から言葉を取捨選択し、簡潔で論理的な文章を書こうとする意識は、どこかでつながっているような気がします。
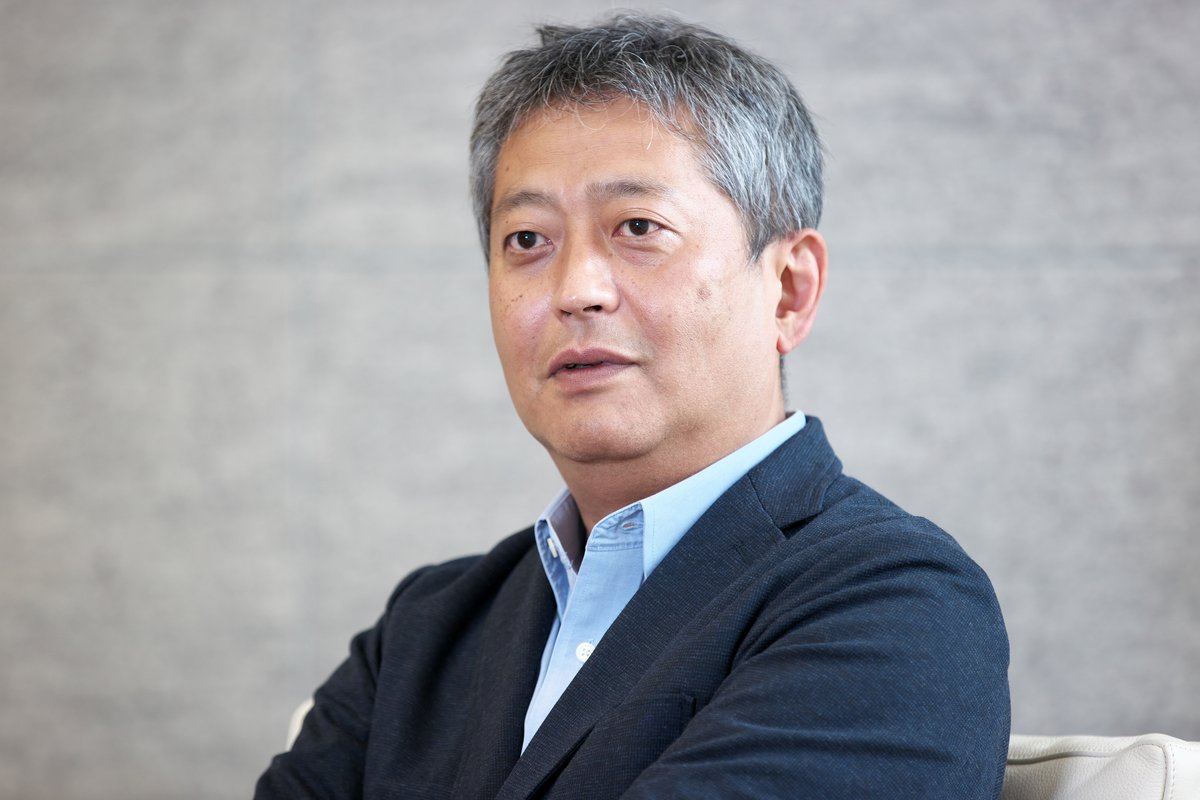
しみず・じゅんいち/1964年、宮崎県生まれ。立教大学社会学部卒。読売新聞論説委員。東京本社社会部デスクなどを経て、2017年より「編集手帳」を担当。直島翔名義で『転がる検事に苔むさず』『恋する検事はわきまえない』『テミスの不確かな法廷』など、小説も発表。
◎筆者プロフィール
いないずみ・れん/1979年、東京都生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。2005年に『ぼくもいくさに征くのだけれど 竹内浩三の詩と死』で第36回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。主な著書に『復興の書店』『「本をつくる」という仕事』『アナザー1964』『サーカスの子』など。

#1 和波孝禧さん「聴く、触る、そして全身で見る」はこちらから。

